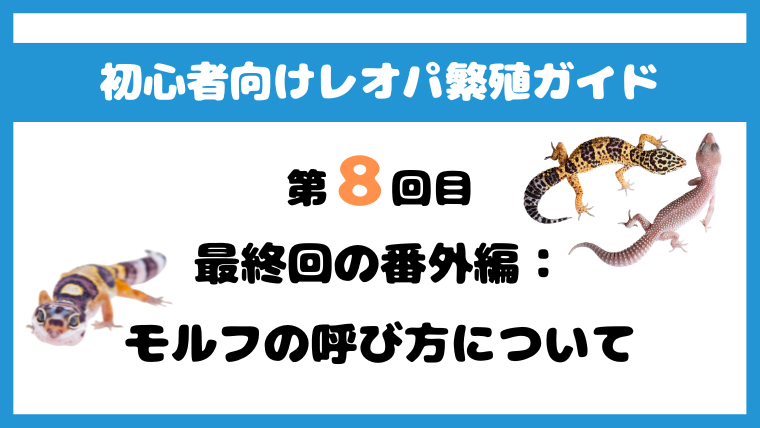「レオパのモルフの呼び方を理解したい!」
「産まれた子供へ親の表現が上手く引き継がれないんだけど、なんで…?」
そんな人のために、2015年からヒョウモントカゲモドキ(レオパードゲッコー、以下レオパ)に囲まれて暮らしている私、のの(X:@leopalife Instagram:@nono_leopalife)がレオパの繁殖ガイドの番外編として、【モルフの呼び方】について解説します。
この【初心者向けレオパ繁殖ガイド】は全8回で展開しており、今回はその第8回目(最終回)です。
【初心者向けレオパ繁殖ガイド】全8回のリンクはこちらから。
- ①基本の”遺伝”から学ぼう!
- ②遺伝子のホモとヘテロを理解しよう!
- ③優性・劣性・共優性遺伝を理解しよう!
- ④モルフの計算方法を理解しよう!
- ⑤ポッシブルヘテロ表記を理解しよう!
- ⑥交配させるペアの選び方と注意点
- ⑦交配から孵化までの過程とポイント
- ⑧番外編:モルフの呼び方について★今ここ
第1回目から読みたい!という方はこちらから読んでみてくださいね。
 のの
ののこのシリーズでは、生物の知識が中学生で止まっている30代半ばの私が、”ちょっと前の私”のような方を対象に、超わかりやすく解説していきます!
簡単に、この【初心者向けレオパ繁殖ガイド】のコンセプトをお伝えします。
このコンセプトは第1回目の記事にも書かれてあることなので、はじめましての方はアコーディオンを開いて読んでいただけると嬉しいです。
初心者向けレオパ繁殖ガイドのコンセプト
【初心者だけど、レオパの繁殖や遺伝について知識をつけたいと思っている人】が、レオパの遺伝を理解し、モルフの計算をできるようになることを目標にしています。
また、実際に繁殖に挑戦するときに知っておかなければいけない、繁殖においての注意点もご紹介します。
全8回の記事を通して、専門的な遺伝の知識というよりは【爬虫類の界隈で通用する程度の知識】や【レオパ飼育者として知っておいて損はない知識】を知っていただき、身につけていただけると幸いです。
さて、前書きが長くなってしまいましたが、この記事のポイントは、以下の通りです。
レオパの呼び方(表記)には「ベースモルフ」「コンボモルフ」「多因子遺伝モルフ」、そして「表現を総称するモルフ」と「ライン名」が存在します。
多因子遺伝モルフは選別交配と系統繁殖によって維持されています。
ライン名はあくまでも血筋で管理された「ブランド名」なので、「表現を総称するモルフ」と混在して名付けてはいけません。
今回の記事は、繁殖ガイドの番外編です。
繁殖ガイドとは直接関係がないかもしれませんが、爬虫類の界隈で通用する程度の知識を持つレオパ飼育者さんを増やしたいという想いのもと展開しているので、ご紹介します。
今回の記事を最後まで読むと、レオパの遺伝性によるモルフの呼び方とライン名の違いを理解できるようになります。
また、「産まれた子供へ親の表現が上手く引き継がれない事態」を理解することができるようになります。



初心者向けレオパ繁殖ガイドの最終回です!
張り切ってまいりましょうー!
レオパの「モルフの呼び方」とは…?
世界中で販売されるレオパには、様々な表記がされています。
「トレンパーアルビノ」という表記を見れば、「アルビノの品種の名前なのかな」ということは、理解できると思います。
しかし、レオパ飼育初心者の方にとっては、これがベースモルフなのかライン名なのか区別つかない方も多いのではないでしょうか?
そして、そもそも「ベースモルフ」というものが、どんなモルフのことを指しているのかも、あやふやな方が多いのでは…?と思います。
実は、レオパのモルフの呼び方には、
- ベースモルフ
- コンボモルフ
- 多因子遺伝モルフ
- 表現を総称するモルフ
- ライン名
が存在します。
そして、「ライン名」や「表現を総称するモルフ」を、「ベースモルフ」と同様に考えてしまうと…



繁殖に挑戦してみたものの、産まれた子供へ親の表現が上手く引き継がれない…!
ということが起こり得るのです。
遺伝の形式と絡めてレオパのモルフの呼び方を理解することで、目の前にいる愛するレオパのことをより一層理解していただきたいと思います。
モルフの呼び方と遺伝
先述しましたが、レオパのモルフの呼び方には、
- ベースモルフ
- コンボモルフ
- 多因子遺伝モルフ
- 表現を総称するモルフ
- ライン名
が存在します。
例えば…
「トレンパーアルビノ」という表記は、メンデルの法則に則った遺伝をするベースモルフの呼び名です。
「タイフーン」という表記は、「レインウォーターアルビノ」と「エクリプス」と「ハイポタンジェリン」と「パターンレスストライプ」を何世代にもわたって掛け合わせたコンボモルフの呼び名です。
「タンジェリン」という表記は、オレンジ色の見た目をしているという表現を総称する呼び名です。
「ブラッド」という表記は、JMG Reptile社によるタンジェリンの特別な血筋であるラインの呼び名です。
これに加えて、「表現を総称するモルフ」と「ライン名」を説明するには欠かせない「多因子遺伝モルフ」をご紹介します。



それでは、ひとつひとつ見ていきましょう!
ベースモルフ
ベースモルフとは、基本的にメンデルの法則に従うモルフのことを指します。



※「遺伝子」「遺伝子座」「優性」「劣性」などの詳しい解説は【初心者向けレオパ繁殖ガイド】①〜⑤を見てみてくださいね。
【初心者向けレオパ繁殖ガイド】全8回のリンクはこちらから。
少し話がずれましたが、遺伝性の検証が進み「メンデルの法則に則る」と確定したもののみが「ベースモルフ」として表記されます。
例えば、ノーマル遺伝子に対して劣性遺伝するベースモルフは以下のようなものがあります。
- エクリプス
- トレンパーアルビノ
- ベルアルビノ
- レインウォーターアルビノ
- ブリザード
- マーフィーパターンレス
等
逆に、ノーマル遺伝子に対して優性遺伝するベースモルフは以下のようなものがあります。
- エニグマ
- GEMスノー
等
そして、ノーマル遺伝子に対して共優性遺伝する(ノーマル遺伝子と優劣の差がない)ベースモルフは以下のようなものがあります。
等
このように、「メンデルの法則に則る」と確定した単一モルフを「ベースモルフ」といいます。
コンボモルフ
コンボモルフとは、複数のモルフ同士の交配を繰り返し、出現したモルフです。
例えば、W&Y(ホワイトアンドイエロー)やマックスノーのコンボモルフが多数作り出されています。
- マックスノーエクリプス
- マックスノートレンパーアルビノ
- W&Yスノーラプター
- W&Yタンジェリン
- W&Yトレンパーエクリプス
- W&Yハイポタンジェリン
- W&Yレーダー
等
この他にも、2つ以上のモルフが何世代にもわたって掛け合わされて作り出されたモルフが多数存在します。
これらを「コンボモルフ」や「複合モルフ」といいます。
多因子遺伝(ポリジェネティック)モルフ
多因子遺伝(ポリジェネティック)モルフは、一言で言ってしまえば「メンデルの法則に従わないモルフ」です。
そのため、例えば多因子遺伝モルフとベースモルフを掛け合わせて交配させた場合、産まれた子供へ親の表現が上手く引き継がれないという事態が生じます。
ここで、多因子遺伝(ポリジェネティック Polygenetic)について詳しめに解説しますね。



ここから少し話が難しくなりますが、読み進めていくうちに理解していただける内容になっていると思います。
多因子遺伝は、アルビノなどの単純なメンデルの法則に則った遺伝とは異なります。
つまり、形質(特徴)が現れるか現れないかに、ひとつの遺伝子が関与しません。
多因子遺伝の特徴は、複数の遺伝子が分子経路レベルで特徴を現すか現さないかの組み合わせによって決まります。



多因子遺伝モルフは、ランダムに「この特徴は現す」「この特徴は現さない」の遺伝子スイッチをオン・オフされた組み合わせの産物だということです。
多因子遺伝モルフは、最終的に安定した特徴が得られるようにするために、選別交配が行われます。
例えば、ジャングルというモルフ同士を掛け合わせればジャングルが生まれ、ストライプというモルフ同士を掛け合わせればストライプが生まれるようにするのです。
これは、しっかりとした系統管理がなされて安定的にジャングルであればジャングルが生まれるように選別交配された結果です。
そのため、系統管理をしっかりと行なった上での繁殖でないと、ジャングルの特徴が現れなかったり単なるノーマル模様が現れたりします。
このように、多因子遺伝モルフは選別交配と系統繁殖によって維持されています。
最近では、多因子遺伝の特徴を持つモルフの多くで、その特徴が固定されるように系統繁殖されています。
そのため、親から子へ特徴が受け継がれる時に再現性が高くなっています。



基本的に、多因子遺伝モルフには「選別交配」と「系統繁殖」が切っても切れないものであることを覚えておいてくださいね。
- エメリン
- タンジェリン
- ジャングル
- ストライプ
- バンディット
等
このように、メンデルの法則に従わず、選別交配と系統繁殖によって特徴が固定化されているモルフを「多因子遺伝(ポリジェネティック)モルフ」といいます。
ここから解説する「表現を総称するモルフ」と「ライン名」は、どちらも「多因子遺伝(ポリジェネティック)モルフ」と深く関係しています。
混乱させてしまうかもしれませんが「遺伝の形式としては多因子遺伝であり、表記としては表現を総称する名前になっていたりするんだ!」と理解してもらえると有り難いです。
表現を総称するモルフ
「表現を総称するモルフ」というのは「見た目を重視して名付けられた(表記された)モルフ」のことです。
例をいくつか挙げますね。
- 「タンジェリン」という表記:オレンジ色の表現(見た目)の総称
- 「キャロットテール」という表記:尾が濃いオレンジ色をしてニンジンのように見える表現の総称
- 「キャロットヘッド」という表記:頭部にオレンジの模様をしている表現の総称
- 「エメリン」という表記:体色に緑色~黄緑色をしている表現の総称
見た目で名付けられたものであることがわかると思います。
混乱させてしまうかもしれませんが、これらはメンデルの法則に則った遺伝をしない「多因子遺伝モルフ」です。
そして、先ほど「多因子遺伝モルフ」で解説した「選別交配」が行われています。
タンジェリンであれば、より濃いオレンジを追求されていますし、キャロットテールであれば、尾の中でもより範囲が広く濃いオレンジ色にすることが追求されています。
遺伝の形式として多因子遺伝であり、表記としては「見た目重視で名付けられたもの」なのだと理解してもらえると幸いです。
ライン名
ラインとは「血統」のことで、同じ血筋で血統管理されたものが同じライン名で表記されます。
例えば、タンジェリンについてです。
タンジェリンは見た目の「オレンジ色」から「表現を総称するモルフ」として「タンジェリン」と表記されます。
そして、タンジェリンは「多因子遺伝」でありメンデルの法則に則った遺伝をしません。
選別交配がされ、より濃いオレンジ色を追求して次世代へとその特徴を受け継いでいきます。
その選別交配の際に、例えば「インフェルノ」というタンジェリンの中でも特定の血筋の中で血統管理して繁殖をしたとします。
そうして生まれた子供は、タンジェリンの中でも「インフェルノ」というラインの名称で表記されるのです。
ここで注意すべきは、生まれてきた子供を「見た目がインフェルノに似ているからインフェルノである」と単なるモルフ名として名付けてはいけないということです。
あくまで、血統が証明されていない個体は「ライン名」での表記ではなく「表現を総称するモルフ」で表記するべきなのです。
実は、びっくりする表記の付けられたレオパの個体を目にすることがありました。
その子に付けられたモルフ名は「ブラッド・エレクトリック het.アルビノ」というものです。
「ブラッド」はタンジェリンの中でも、JMG Reptile社が「ブラッド」というライン名(血統名)で管理し繁殖していたもののことを表記する際の名前です。
また、「エレクトリック」はタンジェリンの中でも、Hiss社が「エレクトリック」というライン名(血統名)で管理し繁殖していたもののことを表記する際の名前です。
そして、この個体には「het.アルビノ」ということで、どこかの交配の中でアルビノも入ってしまっているのです。
この子には本来であれば「タンジェリン het.アルビノ」というモルフ名が付けられるはずです。



ブランド品の鞄を買いに行った時に「ルイヴィトンエルメス」の名札がついた鞄がシャネルのお店に売ってたら、その鞄がどこのブランドのものか、よく分からないですし、そもそもブランドのものなのかも不明ですよね。
ライン名は、見た目ではなく血統重視です。
ここで「表現を総称するモルフ」と「ライン名」をしっかりと区別するためにそれぞれのモルフの解説をすることはしませんが、「「表現を総称するモルフ」と「ライン名」は違う!」と認識してもらえると嬉しいです。
まとめ:モルフの呼び方
レオパの繁殖ガイドの番外編として、【モルフの呼び方】を解説しましたが、いかがでしたか?
もう一度、まとめておくと…
レオパの呼び方(表記)には「ベースモルフ」「コンボモルフ」「多因子遺伝モルフ」、そして「表現を総称するモルフ」と「ライン名」が存在します。
多因子遺伝モルフは選別交配と系統繁殖によって維持されています。
ライン名はあくまでも血筋で管理された「ブランド名」なので、「表現を総称するモルフ」と混在して名付けてはいけません。
今回で【初心者向けレオパ繁殖ガイド】も最終回でした。
最後まで読んでくださった方、ありがとうございました!!!
全8回を通して、少しでも【爬虫類の界隈で通用する程度の知識】や【レオパ飼育者として知っておいて損はない知識】を知っていただけるきっかけになっていれば幸いです。



繁殖に挑戦する際には何度も読み返していただき、より安全な繁殖を心がけていただきたいと思います。
モルフ計算もモルフの名付け方もしっかりマスターしてくださいね。
【初心者向けレオパ繁殖ガイド】全8回のリンクはこちらから。